
小さな改善で成果が変わる 行動経済学を使ったファンドレイジング ~寄付者を「動かす」コミュニケーションの第一歩 9/14(土)13:50~15:00
スピーカー
平尾千絵 氏(株式会社ファンドレックス エグゼクティブディレクター)
学んだポイント
・データ化しやすいホモ・エクノミクス=経済人を前提に今の経済学は考えられている。しかし、実際に生身の人間は経済人とは全然違う。無駄な買い物もするし、非効率なことを選択したりもする。行動経済学とは、人間の心理的感情的側面の現実に即したものである。行動経済学、心理学、脳科学を活用し、どうやったら寄付者が気持ちよくなるか、顧客満足度が上がるかについて、真剣に考え、ファンになってもらう。偏愛される。
・行動経済学は、理論を知っても回避できない=人が不合理な部分。脳にだまされている。
・寄付者にできるだけ心理的ストレスをかけず、気持ちよく決済まで進んでもらう導線をつくる。
・選べる自由がありすぎると選べない。選択肢が多いほど選ぶのが難しくなり、消費者の満足度が下がる。消費者に選ばせない、選択のストレスから解放してあげる。
・同じ内容でも伝え方の違いで判断が変わる=フレーミング効果。応用として、マンスリーの会費について、「年額1万2千円」より、「月1,000円」の方がフレームが安いため、安く感じる。
・同じ方向を向いて話すのは大事。支援者と話す際は対峙せずに同じ方向を見た方が良い。
・直前に見た数字で金額の価値が変わるアンカリング効果から、寄付は高い額からお願いする。
・人のためにお金を使うと幸福度が上がるように人間は進化してきており、生まれながらそう感じるように設計されている。
・AとBの選択肢がある際、おとりの選択肢B’(Bより少し劣る)を設けることで、もとはAの方が人気であっても、Bが人気になるようにひっくり返ることがある。脳がだまされて、価値が相対的に決まってしまう。
・寄付額の表示をする際には、選択肢を複数設け、デフォルトを中間の数字にしておくと、極端の回避性から、両極は心理ストレスがかかるので選びにくく、またナッジ理論からデフォルトの値が選ばれやすいため、プレースホルダーにこちらが求める金額を予め入れておくことが有効。
・スマホの縦画面、タッチ入力に適した寄付フォームの設計も重要。きちんと取り入れている事例がUNCHR協会、ユニセフ、国境なき医師団。
・ランディングページ(LP)を設けることは鉄則。参考になるのがユニセフのLP。ところどころに寄付するボタンが設置されている。LPなのにあちこちにリンク張るのはNG。(例、理事会名簿や活動報告書など)。ずっとここにいてもらう。どこにもいかせない。LPを見て寄付したい人には、何のストレスもなく、寄付の決済までこのページですべて完結させてあげる。
・LPを最後まで見たものの寄付する選択をしなかったユーザーの受け皿として、LPの一番下にFacebookやTwitterやメルマガの登録ボタンを設置しておくと良い。せっかくここまで読んでもらった人をただで返してしまうのはもったいない。なんらか接点をもつような仕掛けを設ける。
・LPや寄付ページには寄付したい人しかこない。その方に団体がこれくらいもらいたいという意思を潜ませる。それにより支援者をストレスから解放する。決して押しつけではない。



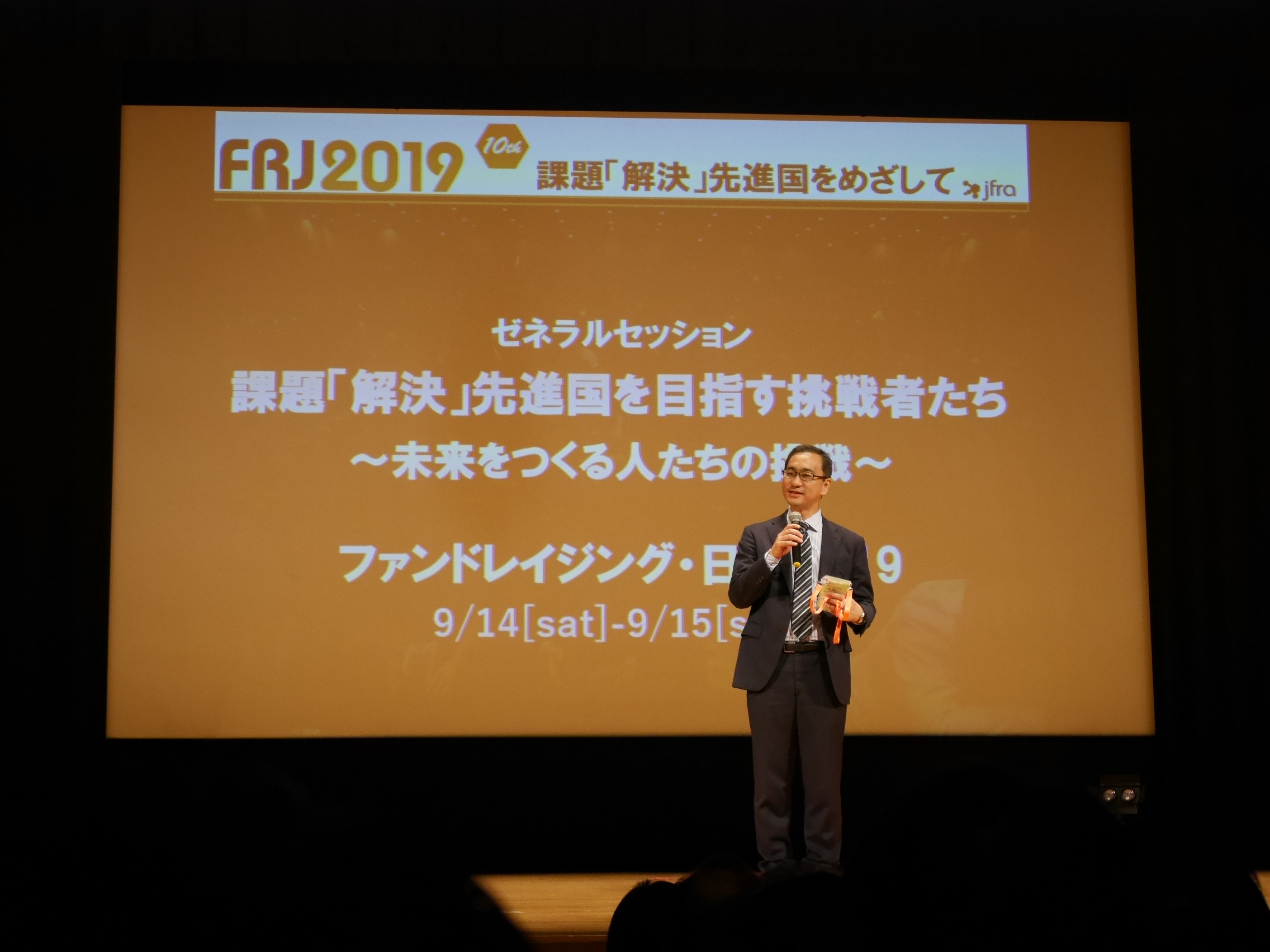
コメント